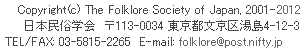HOME > 談話会開催記録 > 2009年 > 第847回
第847回 日本民俗学会談話会
「さらば「民俗学」―新しい《民俗学》の再構築に向けて(5)―」( 国際ワークショップ「文化遺産と韓国民俗学」)
民俗の競演と「芸術」化
南根祐(ナム クヌ)(東国大学校)
日帝植民地下において隠滅の道を歩んだ朝鮮の郷土娯楽であるが、1930年代前半、突如として復興の機運が高まる。黄海道(ファンヘド)鳳山(ポンサン)地方で行われていた仮面劇(カミョングッ)もその一つだ。本発表では、この「鳳山(ポンサン)仮面劇(カミョングッ)」の近代を議論の起点として、ローカルな民俗が各種競演大会を経て、国家公認のナショナルな文化財として転化する過程を探った。特にこの民俗の文化財化の過程において、芸術以前の民俗事象が構造的に芸術化を追求せざるを得ない制度上の問題を考察し、合わせて、その民俗の芸術化を理論的に後押しした韓国民俗学の意思と欲望について検討した。その結果を整理すると、以下のとおりである。
韓国において「民俗芸術」という用語が登場したのは、1930年代に至ってからのことである。植民地朝鮮において繰り広げられた30年代前半の農村振興運動と後半の厚生運動を背景として、「民衆娯楽」、「郷土娯楽」、「農村娯楽」などの語と共に広く使われ始めた。そして1938年、朝鮮日報社が主催した「民俗芸術大会」を始め、この「民俗芸術」の競演大会は、中日戦争以後の総力戦体制の下でしばしば行われた。これを通じて明朗な雰囲気と協同の精神を助長することにより、いわば「銃後朝鮮」の生産力を増強し、その増産活動に必要な強靭な持久の精神を確保するためであった。こうした農楽大会を始めとする競演大会は、解放後の4、50年代にも頻繁に開かれた。そして問題の「全国民俗芸術競演大会」が1958年に登場することになる。本来この大会は、大韓民国政府の創立10周年を慶祝するための一回性の行事として企画されたものだったが、1961年以後、例年の行事として行われることになる。この国家主導の競演大会は、1999年に「韓国民俗競演祝祭」と改称し、2009年現在、第50回を迎えている。
このような民衆の慰撫のための娯楽性を指向した競演大会が、芸術性を追求することになった直接的な契機は、1962年の文化財保護法制定とその施行だった。同年、第3回「全国民俗芸術競演大会」が開かれ、その審査委員として文化財委員を歴任していた民俗学者らが大挙して参加すると同時に、「民俗芸術」の優劣は、民俗の原形性と芸術性という二つの評価指標によってより分けられることになった。本来、二律背反的なこの二つの指標は、結果的には競演大会に参加したすべての民俗の芸術化を助長することになり、大会で入賞したローカルな民俗は、その原形性と共に芸術性を公認されることになった。芸術上の価値が要求される重要無形文化財の有力な指定通路として、競演大会が活用されてきた理由はここにある。2009年現在、文化財庁の公式の統計によれば、総114種目の重要無形文化財のうち1/3に近い35種目は、競演大会を通じて発掘された。
ここで問題なのは、その重要無形文化財の指定に、カンガンスルレをはじめとする車戦(チャジョン)遊び(ノリ)、木牛戯(セモリテギ)、綱引き遊び(チュルタギギ)などの民俗遊び(ノリ)が多数含まれるという点だ。もちろん現実的には、無形文化財指定の審議を行う文化財委員の大半が民俗学者として競演大会の審査委員を引き受けるという閉鎖的な人的構成と、無形文化財の自己充足的なテキスト構成を前提としてはじめてそれが可能なのかもしれないが、この問題は、文化財保護法が規定する「無形文化財」と「民俗資料」の関係、特に無形「民俗資料」との関係を韓国民俗学がどのように認識してその理論的枠組みの材料を提供しているのかという点と関連付けて省察する必要がある。
韓国の場合、民俗の文化財化には二つの方式が存在する。一つは無形文化財として指定すること、もう一つは民俗資料として指定する方法だ。ここで私たちが注目すべきは、無形の民俗資料は、指定以後は重要民俗資料には指定されないという点だ。重要民俗資料の指定は、「衣服、器具、家屋、その他のもの」と同じ類型の場合に限定される。なぜそうしたのだろうか?無形の民俗資料を法規定に含み、その上、その細部の指定種目まで具体的に明示しておきながら、実際には指定制度を導入しなかった理由は何か?推論に過ぎないかもしれないが、次のいくつかの要因を想定してみたい。すなわち、文化財委員として当時、学問的権威を寡占した民俗学者らの認識論と日本の文化財保護法の受容過程、民俗芸術競演大会の在り方などと関連する。
敷衍といえば、無形文化財のうち無形民俗資料を含もうという民俗学者らの「領域拡張」論と、その本質になった両者の「融通的な」指定基準、そして民俗資料選択制度の脱落とそれに伴う民俗消滅の危機意識、及び民俗の芸術化を助長する競演大会の在り方などが相互に共鳴を起こすことによって「民俗資料」の「無形文化財」化が暗黙的に許容され、その許容の種目と頻度が増え、やがてそれが既成事実へと変貌してゆく。そうした既成事実化の過程で、民俗の資料化に精通した民俗学専門の文化財委員らは‘自然に’言説的権威の優位を占めることになり、それを梃子として、無形文化財制度運営のヘゲモニーを握ることができたのだと考えられる。(訳:田中理恵子)
民俗の文化財化とグローバル化−安城男寺堂(アンソンナムサダン)バウドギ風物遊び(プンムルノリ)を中心として−
丁秀珍(チョン スジン)(西江大学校社会科学研究所)
韓国の無形文化財制度は、民俗の固有文化を発掘、保存するという民族主義的理念の下、多種多様な地域の生活様式を、国家を代表する文化的表象として選び、分類し、目録化することによって成立した。しかしその過程において、成果と同等の問題点もまた産出される。これまで比較や評価の対象とならなかった各地域の生活様式が、無形文化財として選別、指定される一方で、指定されたものとそうでないものとの間に序列が生じた。また国家レベルでは指定できないものを地域レベルで指定し、その指定のレベルによる序列化が進展した。 結局、無形文化財制度という‘ナショナル・スタンダード’を通過した文化形態の価値と意味は、その制度以前の地域の脈絡に遡及して把握されるに値するものではなかった。
ところで、1990年代以後に強く吹き始めた‘グローバル化’の風は、民俗と無形文化財を囲んだ既存の地形を急激に変化させた。何より無形文化財を解釈する主体が、国家から地域へと変化するという点は注目するに値する。本発表は安城(アンソン)の事例を対象として、地方自治制の実施以後、地域が民俗と無形文化財をどのように解釈、活用しているのか、地域の政治経済的目的によりその意味がどのように躍動的に変化しているかを明らかにする。この事例は、韓国近代化の過程において進行した社会各部門の中央集中化によって、人的、物的資源の枯渇を経験してきた地域が、現在選ぶことができるきわめて有限な選択肢の中の一つとして無形文化財を活用するという局面を見せるものだ。
1994年、地方自治制が実施されて以来、外見上、最も眼に触れる変化は、地域祭りの爆発的な増加である。各地方自治体は、地域祭りの開催目的として、地域住民の結束、地域経済の活性化を標榜としてきた。特に各地域の無形文化財を、地域祭り及び国際行事に連係させる方案は、中央政府の文化政策の次元においても積極的に推奨された。この法案は、無形文化財に付与された象徴的価値を地域が有用/流用できるようにして、地域祭りの商品性を向上させる効果を発揮するものだった。
安城(アンソン)市が地域文化に関心を持ち始めたのも、このような背景と無関係ではない。 安城(アンソン)市は、男性だけで組織された男寺堂(ナムサダン)牌(ペ)を導いた伝説上の女性“バウドギ”とともに、彼らの風物(プンムル)遊びを地域活性化のための文化資源として注目し始めた。以後、民俗学的知識を土台としてバウドギ伝説の歴史化が進められ、1997年、彼女を頂点とした‘安城(アンソン)男寺党(ナムサダン)風物(プンムル)遊び(ノリ)’が無形文化財に指定されるに至る。
しかしこの風物(プンムル)遊び(ノリ)は、国家の‘重要無形文化財’でない‘市道指定無形文化財’として指定された。熱心に構築した地域文化が重要無形文化財に指定されなかった状況から、むしろ市が介入できる余地は相対的に大きくなった。こうして安城(アンソン)が考案したのは、無形文化財保存会とは別に市立の風物(プンムル)団を創立することだった。そして風物(プンムル)団を通して、中央政府ではなく世界と直接交流するという方案だった。その方案は窮極的には、‘エディンバラ・フェスティバル’のような世界的な公演フェスティバルに出演し、韓国最高の公演芸術品として認められることを目標にするということだった。数回に渡る海外公演と祭りの成功は、その可能性を証明してくれた。
しかし安城(アンソン)の事例は、地域に委ねられた‘地域文化のグローバル化’の企画の中で、今日、無形文化財が置かれた逆説的な状況を見せてくれる。文化資源の価値を極大化して地域の文化的求心点を用意するために、無形文化財に指定されることが必要だったが、すでに世界的な公演商品として跳躍する場合、無形文化財はむしろ妨げとなった。
まず無形文化財保存会の年配の会員たちは、公演商品の開発には役に立たなかった。科学的な教育方法の導入に、既存の位階秩序は妨げとなった。無形文化財の原形保存の原則も、完成度の高い公演芸術品を作るためには廃棄しなければならないものだった。さらには、風物(プンムル)団内部で発生し始めた大小の葛藤を解消するため、保存会と風物(プンムル)団の分離は避けられなかった。しかし、風物(プンムル)団に移動した保存会の若い伝授者らは、風物(プンムル)団では安定した月給が保証されているために保存会には復帰せず、保存会と風物(プンムル)団の分離は、最終的には無形文化財の指定解除を招かざるを得ない問題であった。これこそが、無形文化財がグローバルな文化商品として再構成される過程でもたらされた逆説的な結果として、無形文化財が抱えるジレンマに違いないと思われる。(訳:田中理恵子)